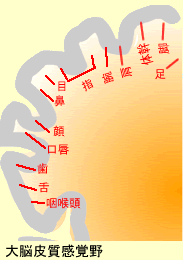|
1.感覚の分類 ヒトは熱い、冷たい、痛い等いろいろなことを体で感じたり、目や耳を使って物を見たり、音を聴いたりできます。感覚というのはいろいろな外からの刺激を体の特定の器官が感じとり(感覚受容器)、認識することです。感覚は大きく分類すると下記のように分類されます。 (1)体性感覚(Somatic Sensation)
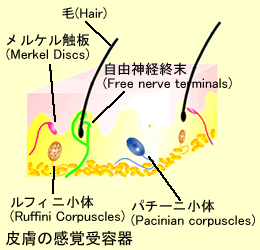
触覚(何かが触れている感覚):メルケル触板、 マイスナー小体、ルフィニ小体、自由神経終末
2点閾値:皮膚の近い2点(たとえば5mm間隔)を先端が尖ったもので触れてみると
2点と感じる部分と1点にしか感じない部分があります。2点と感じる最小距離を2点閾値と言い、体の場所によって2点と感じる距離が違います。たとえば、口唇、顔、指先等は2点閾値が小さい場所です。 (2)内臓感覚(Visceral Sensation)
(2)内臓痛:内臓におこる痛みのことです。受容器は自由神経終末です。内臓痛は皮膚の痛みとは違い、非常に限局した傷害では起こらず、臓器が広範囲に損傷を受けた場合に感じられます。痛みの原因となるものに虚血、化学刺激、けいれん等があります。痛みは神経を通って脊椎から脳へと伝え
られますが、その際、皮膚の特定の部分に不快感や痛みを感じることを 関連痛(Referred Pain)と言います。たとえば肝臓疾患の時に右肩、心臓異常の時に左上腕に痛みや不快感を感じることがあります。
これは脊髄で内臓からの感覚神経と皮膚からの神経が集まり、大脳皮質へ伝達される際、脊髄の同じレベルからの内臓神経痛を中枢が皮膚からの痛覚刺激として認識するからです。関連痛は内臓疾患の診断に非常に重要です。 2.体性・内臓感覚の分子機構例 A.触覚の分子機構:最近、ほ乳類において触覚に関係があると思われる分子が同定されました。Brain sodium cannel1 (BNC1)というナトリウムチャンネル蛋白(イオンチャンネル)は毛根周囲に分布する自由神経週末に発現していることがわかりました。この蛋白の発現をブロックした動物と正常の動物を比べると軽度の機械的刺激に対する反応がブロックした動物において低下しています。生体内では機械的刺激によってイオンチャンネルがオープンし、レセプターポテンシャルが発生します。それが神経細胞膜の脱分極を起こし、神経のアクションポテンシャルが発生、中枢へ感覚刺激が伝わります。この蛋白以外にも神経週末やメルケル触板に発現している別のイオンチャンネルも同定されています。これらの蛋白にホモロジーが高い同等の機能を持った蛋白分子が線虫(C。elegans)にも発現しており、生物進化の過程でよく保存されていることがわかります。 B. 痛覚の分子機構:Capsaicinという唐辛子の成分に対する受容体であるVR1はカチオンに対するイオンチャンネルの一種であり、感覚神経に発現しています。このイオンチャンネルは熱などによる痛覚刺激に反応することがわかっています。またATPに対する受容体であるP2X3レセプターも痛覚刺激に関与しています。
3.感覚の伝導路 体性感覚のシグナルは脊髄の後根(後ろ側)から脊髄に入り、脳内にある視床(感覚の中継路)核に向かって脊髄を上行します(脊髄視床路)。温度覚、痛覚、触覚などの1次ニューロンは脊椎後根から脊椎に入り、神経繊維を変えて(2次ニューロン)対側の脊椎内を上行し延髄から視床に入ります(左図緑)。さらに視床で3次ニューロンに変わり大脳皮質の感覚野に入ります。深部感覚の神経繊維はそのまま同側の脊椎を繊維を変えずに上行し、延髄に入ります。延髄で神経繊維を変え(2次ニューロン)対側の視床に入ります(赤の経路)。視床に到達したシグナルは3次ニューロンとなり大脳皮質の感覚野という場所に伝達されます。感覚刺激を受けた体の場所によって感覚野の神経が連絡する場所が異なります。 感覚の投射(Projection):末梢の受容器からの感覚刺激は大脳の感覚野に伝達し処理されますが、感覚は刺激を受けた場所に感じます。これを感覚の投射といいます。
4.大脳皮質の感覚野
大脳皮質は表層から数えてIからVIの6層からなっています。感覚シグナルはまず第IV層の神経細胞を興奮させ、シグナルは上方と下方に伝わります。このように大脳皮質では直径0.3から0.5mmで約10000個の神経細胞を含むコラム(円柱)構造が多数あります。このコラムの中で身体各部の受容器からのシグナルを処理しています。
|
 (1)
(1)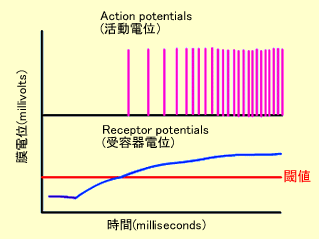 感覚の受容器(レセプター)が機械的刺激を受けると電位が発生します。この電位は最高100ミリボルト程度でこれは活動電位と同程度です。受容器の刺激によって電位が閾値(Threshold)を越えると神経線維に活動電位(Action
potentials)があらわれ始めます。ここで注目すべきことは、受容器の電位が最高値にむかって上昇し続けると、神経線維の活動電位は電圧が上昇するのではなく、神経インパルスの頻度が増加することです。これはアナログ信号からデジタル信号への変換にあたります。
感覚の受容器(レセプター)が機械的刺激を受けると電位が発生します。この電位は最高100ミリボルト程度でこれは活動電位と同程度です。受容器の刺激によって電位が閾値(Threshold)を越えると神経線維に活動電位(Action
potentials)があらわれ始めます。ここで注目すべきことは、受容器の電位が最高値にむかって上昇し続けると、神経線維の活動電位は電圧が上昇するのではなく、神経インパルスの頻度が増加することです。これはアナログ信号からデジタル信号への変換にあたります。